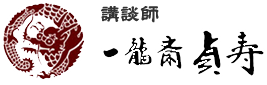ご挨拶
「独参湯」という薬湯をご存じでしょうか。
江戸時代の薬で、万病に効く起死回生のきつけ薬のことです。
なんにでも良く効くところから、転じて、歌舞伎の世界では、常に大当たりをとる人気作品の事を「独参湯」と例えられるようになったそうです。
その代表的な作品が、「仮名手本忠臣蔵」…赤穂義士伝です。
すでに天明のころには、「忠臣蔵の狂言、いつとても大当たりならぬ事なき」といわれ、忠臣蔵は、どんな不況な時でも大当たりをする「芝居の独参湯」と例えられる様になりました。
いま、このコロナ禍において、演芸界は一変しました。
お客様の前で高座に上がる、という当たり前のことが出来なくなりました。
こんなこと、だれが想像したでしょうか。
恐る恐る日常を取り戻すべく動き始めても、いままでのように、「ぜひ来てください!」と声高に言うことすら憚れる中、自主公演を行うことは賢いことではないかもしれません。
でも、いまだからこそ。
「忠臣蔵がやりたい」
そう、思いました。
赤穂義士伝は、一龍斎のお家芸でもあり、私自身が講談師を志すようになったきっかけでもあります。
こんな時代だからこそ、いま私が出来るすべてを込めて、赤穂義士伝を読ませていただきます。
東京では、GOTOキャンペーンも始まり、劇場の入場者数の制限も緩和されました。
でも、新規感染者数が減ったわけではなく、誰もが気軽に足を運べる状況ではありません。
そのため、当公演におきましては、入場者数を制限し、出来る限りの感染予防対策を施したうえで開催させていただきます。
また、ご来場が難しい方のために、動画配信もご用意いたします。
講談を、演芸を、心置きなく楽しめる日が一日も早く戻りますよう。
「独参湯」に願いをこめて。
一龍斎貞寿独演会~寿会~
2020年10月23日、広小路亭にて開催させていただきます。
会場でも、ご自宅でも、
お楽しみいただけたら幸いです。
ご予約、お待ちしております。
一龍斎貞寿 拝
出演者紹介
一龍斎貞寿
2002年 一龍斎貞心門下、入門
2003年10月 講談協会前座
2008年10月 二ツ目昇進
2017年4月、真打昇進
現在、講談協会定席の他、地域寄席、文化庁による学校公演、講談教室などでの講演・高座。都内歴史ガイド、イベント・結婚式などの司会…など、明るい芸風を生かし幅広く活躍中。
2012年、三味線、杵屋松紀三とユニットを結成。四谷怪談、源平盛衰記、赤穂義士伝などの古典講談に、生の音曲をつけた立体講談を毎年口演。
杵屋松紀三
幼少期に母親である杵屋 佐登糸に手ほどきを受け、杵屋 佐登代に師事。
平成6年、佐門会にて「杵屋 佐登純」の名前を頂く。
その後、五代目杵屋 勝松に師事。
平成22年、杵勝会にて「杵屋 松紀三」となる。
糸音会を主催し、若い世代へ広める活動や指導に力を入れている。
また、地域に密着した和太鼓グループ「荒魂」の立ち上げに加わり、指導や楽曲提供、演出に携わる。
平成24年、講談と和楽器のコラボレーション公演「いなせなレボリューション」にて、一龍斎貞寿の下座を勤め、以降、講談に生の音曲をいれた企画公演「話音」を定期的に開催、好評を博す。
チケットのご予約
会場へのご案内
お江戸上野広小路亭
東京都台東区上野1丁目20−10